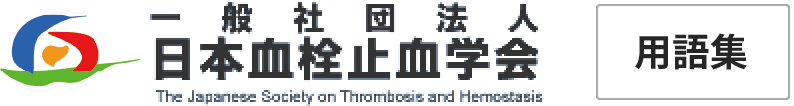- 大分類
-
- 凝固
- 小分類
-
- 治療
心房細動と抗凝固療法
解説
Framingham研究は34年間の観察期間内の「脳卒中」発症に寄与する因子として心房細動、心不全、高血圧、冠動脈疾患のインパクトを示した。外来通院中の動脈硬化・血栓性疾患の世界共同前向き観察研究でも、心房細動合併症例では1-4年の観察期間内の「脳卒中イベント」、「死亡イベント」が心房細動非合併例よりも高いことが示されている。
「脳卒中」が「心房細動」で多いのであれば、抗血小板薬より血栓イベント発症予防効果は強いが出血イベント惹起率も高い抗凝固薬を「心房細動」に用いて「脳卒中」を予防しようとの方向が生まれた(参照:CHADS2スコアと抗凝固療法)。CT、MRIなどの画像診断が広く普及している本邦で「脳卒中」と診断される症例はまずいない。弁別の難しい症例もあるが、「脳出血」と「脳梗塞」には弁別されている。病態生理を重視すると「心房細動」にて「血流のうっ滞した左房に形成された血栓が脳に塞栓」して、「心原性脳塞栓症」を惹起するようにも考えられる。しかし、Framingham研究以来の科学的疫学研究において、心房細動症例における心原性脳塞栓症の発症リスクを明確に示した研究はない。
抗凝固薬ワルファリンは比較的使い難い薬剤であった。以前から確立していた僧帽弁狭窄症に対する抗凝固薬以外に、非弁膜症性の心房細動でも抗凝固薬が「脳卒中予防」に役立つとされても、ワルファリンの普及は限局的であった。僧帽弁狭窄症以外の心房細動では血栓塞栓症リスクは僧帽弁狭窄症に比較すれば、はるかに低いのでワルファリンの有用性も実感できる水準ではなかった。実際、日本の臨床家はPT-INR 2.2以上(参照:プロトロンビン時間〔PT〕)などでは出血イベントリスクの増加が無視し得ないことを体感していた。
経口トロンビン阻害薬、経口活性化凝固第X因子阻害薬(Xa阻害薬)は凝固因子に対する直接的かつ可逆的な酵素作用阻害薬である。僧帽弁狭窄症を合併した心房細動、人工弁置換後など真に血栓性が亢進した病態ではワルファリンに勝る効果は期待できない。そこで、イベントリスクがそれほど高くはないが、無視できるほどでもない「非弁膜症心房細動」を対象として「脳卒中・全身塞栓症」を有効性の一次エンドポイントした試験を行った。抗凝固薬として、出血イベントは当然増加すると見込んで、確立された標準治療がないことを背景に「PT-INR 2-3を標的としたワルファリン治療」を仮の標準治療として、この仮の標準治療に対する有効性、安全性を検証した。
ワルファリンの自由度を縛り、負けないために必死の工夫をしたにもかかわらずリバーロキサバン、エドキサバンでは「INR 2-3を標的としたワルファリン治療」に勝る有効性を示すことができなかった。経口トロンビン阻害薬ダビガトランは高容量にて有効性を示したが、試験がオープンラベルであったため科学的価値は低い。アピキサバンは有効性、安全性の両者において科学的に「INR 2-3のワルファリン治療」に勝る優越性を示したが、薬剤開発の第三相試験は実臨床にて、INRを1.7程度にコントロールしている日本の臨床医に影響を与えるものではなかった。真に血栓イベントが心配な僧帽弁狭窄症、機械弁では役にたたず、価格はワルファリンの10倍以上という実態では、経口トロンビン阻害薬、Xa阻害薬が必要な病態は限局される。